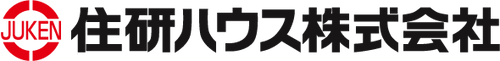暖かい家のメリット・デメリット
「暖かい家」には、「快適な生活を送ることができる」「光熱費があまりかからない」「結露を防げる」などのメリットがある一方、「換気をこまめに行わなくてはならない」「灯油ストーブやガスストーブは使用できない」「閉鎖的な空間になる可能性がある」といったデメリットもあります。
ただし、デメリットをあらかじめ把握した上で家づくりを行えば、ぬかりなく暖かい家を建てることは可能です。ここでは、暖かい家のメリットとデメリットをご紹介します。
高気密・高断熱住宅に欠かせないUA値・C値・Q値とは?
家づくりを検討していると、「UA値、C値、Q値」という言葉がよく出てきます。「一体何の数値?」と気になる方もいるでしょう。
UA値、C値、Q値とは、住宅の性能を表す数値。UA値とQ値は「どれくらいの熱量が家の外に逃げやすいのか」を表した値、C値は「家にどれくらいのすき間があるのか」を示しています。
Q値は、2013年の省エネ基準改正以前に使われていた数値ですが、換気による熱量の損失も考慮できるため、今でも活用しているメーカーが少なくありません。
断熱等級とは?
断熱等級とは、家の断熱性能を表す指標のことです。等級には1~7までの7段階があり、等級が大きいほど熱の出入りが少ない、断熱性能が高い家であることを示します。
断熱等級は2022年3月までは4が最高等級でしたが、2022年4月に等級5が、同年10月に等級6と7が新設(※)されました。2025年以降の新築住宅では断熱等級4以上、2030年以降は等級5以上が義務化(※)。このため、これから家を建てる方は最低でも等級5、できれば等級6を目指すのがおすすめです。
※参照元:SUUMO(https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chumon/c_knowhow/dannetsutokyu/)
断熱材の種類と性能
「暖かい家」に欠かせない断熱材。断熱材にはたくさんの種類があり、それぞれ性質や価格が異なります。
ガラスや岩を細かい繊維状にして凝縮させた「無機繊維系断熱材」には、グラスウールやロックウールがあります。火災に強く価格も安いのですが、水や湿気を吸うと断熱効果が低下する場合があるので注意しましょう。ウレタンフォームなどの発泡プラスチック系断熱材は、軽量かつ施工が簡単なため、最近特に多く利用されています。
高気密・高断熱の家の定義や基準とは?
高気密・高断熱の家とは、「気密性・断熱性を高めた、外気温の影響を受けにくい住宅」のことです。ただし、日本には高気密・高断熱の家に対する国の明確な基準はなく、各ハウスメーカーが独自に定義づけして販売している状態です。
判断の基準になっているのが、気密性を示すC値と、断熱性を示すUA値です。北海道なら、気密性はC値1.0㎠/㎡以下、断熱性はUA値0.46W/㎡K以下を目安にすると良いでしょう。ぜひ比較・検討する際の参考にしてください。
暖かい家をお得に建てるには?
「暖かい家」を実現するためには、気密性や断熱性のほかに、窓や換気システムに注意することが大切です。それぞれ費用はかかりますが、だからといって、必ずしも多額の費用を出さなければならないわけではありません。ローコスト住宅でも、注意するポイントさえ押さえていれば暖かい家を実現することは可能です。
ここでは、暖かい家にするために注意したいポイントと、それぞれにかかる費用をご紹介します。ぜひ、家づくりの参考にしてください。
間取りを工夫して夏涼しく冬暖かい家をつくる方法
一年を通して温度環境が整っている家にするためには、間取りにも配慮が必要です。例えば、自然エネルギーをうまく取り入れる設計。住宅の中でも特に外気温の影響を受けやすい窓は、日射取得(遮蔽)を意識して大きさや場所を決めることで、エアコンを使わなくても冬の昼間に20℃近い室温を得ることが可能です。
部屋の形状や間取りをシンプルにすることも大切です。室温ムラがなくなり、少ない空調でも快適な室温を保つことができます。
外断熱と内断熱の違い
外断熱が建物全体を外側から覆うように断熱材を入れるのに対し、内断熱は柱の間に断熱材を入れて外気の出入りを遮断する工法です。
外断熱は内断熱より施工費がかかるものの、断熱性・気密性に優れているため、北海道のような冬の寒さが厳しい寒冷地では外断熱がおすすめです。また、施工できる業者は限られますが、外断熱と内断熱の良いとこどりをしたハイブリッド工法という選択肢もあります。
トリプルガラスのメリット・デメリット
トリプルガラスの窓は、3枚のガラスの間に空気やガスを封入した構造です。単板ガラスや複層ガラスと比べて、熱の出入りを抑え、優れた断熱性を発揮するのが大きな魅力です。また、室内の熱が逃げにくいため、エアコンの効率を向上させる効果も期待できます。デメリットとしては導入費用が高いこと、窓自体が重く開閉しにくいことが挙げられます。トリプルガラスを採用するかどうかは、建設する地域や優先するポイントに応じて判断することが重要です。
コールドドラフト現象とは?
コールドドラフト現象とは、暖められた空気が冷たい窓ガラスに触れることで冷却され、足元に冷気が滞留する現象です。これにより部屋全体の温度差が生じ、足元が冷える原因になります。暖房効率が悪くなり、光熱費がかかる理由にもなるため、北海道で家を作る際なら事前に対策しておくと良いでしょう。
高断熱な住宅には「窓」選びが大切
高断熱住宅の鍵は、窓の断熱性能にあります。冷暖房効率を高め光熱費を抑えるためには、適切な窓の種類や素材選びが不可欠です。このページジでは、高断熱に適した窓の種類(複層ガラス・トリプルガラス)や、フレーム素材(樹脂・木・アルミ樹脂複合)に焦点を当て、最適な選び方と設置のポイントを解説。さらに、断熱性を高めるLow-Eガラスや真空ガラスの活用法も紹介しています。
ヒートショックを防ぐ家づくりのポイント
ヒートショックとは、大きな寒暖差によって血圧が急激に変動する現象のことです。最悪の場合、心筋梗塞や脳卒中など命にかかわる症状を引き起こしてしまう危険性があります。ヒートショックを防ぐには、家全体をまんべんなく暖かくする高気密・高断熱にこだわった家づくりが重要です。健康で快適に暮らすための家づくりのポイントを解説します。
吹き抜けは寒いって本当?
吹き抜けが寒いと感じる理由には、暖かい空気は上昇して、冷たい空気は下降するといった空気の流れが関係しています。上下階で温度差が生じるため、吹き抜けのある1階部分は暖房をつけていても寒さを感じやすくなってしまうのです。暖かい吹き抜けリビングをつくるために知っておきたい、断熱性・気密性を高めるポイントを解説します。
平屋は寒いって本当?
平屋に憧れているけれど、「平屋は寒い」「平屋は底冷えする」という噂が気になっているという方もいるはず。平屋に寒くなりやすい要因があるのは事実ですが、設計にちょっとした工夫を加えれば北海道でも暖かい平屋を実現することは可能です。平屋が寒くなりやすい要因や暖かい平屋をつくるためのポイントについて解説します。
ZEHとは?
ZEH(ゼッチ)は「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略で、家庭で使うエネルギーと、自宅でつくるエネルギーのバランスをゼロ、またはプラスにできる住まいのことをいいます。
「夏の暑さや冬の寒さをガマンする」のではなく、家の断熱性を高めたり、省エネ設備を取り入れたりすることで、快適さをそのままに省エネを叶えるのがZEHの特徴です。さらに光熱費の削減や、災害への備えなど、暮らしにうれしいメリットもたくさんあります。
北海道でZEHは現実的?
近年は「ZEH(ゼッチ)」という言葉を目にする機会も増え、省エネや環境に配慮した住まいとして注目されています。
一方で、冬の寒さが厳しく、積雪も多い北海道では、「ZEHの実現は本当に可能なのか」「太陽光発電が難しいと、ZEHの認定は受けられないのでは」と疑問を感じる方も多いでしょう。
こちらでは、北海道でZEHは現実的なのかについて紹介します。