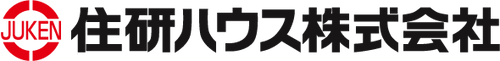せっかく家を建てるなら「暖かい家」が良い、とお考えの方は多いでしょう。暖かい家を建てるポイントの一つが床。床や基礎などに断熱材を施し、床下からの冷気を防ぐことが大切です。ここでは、家が寒くなる原因や家を暖かくする方法、暖かい家の選び方などをご紹介します。

伊藤修平さん
住研ハウス苫小牧本社の建築部長。暖かい家づくりの豊富な知識に限らず、2級建築士や増改築相談員・既存住宅現況検査技術者・BIS-M・外壁診断士など多数の資格を持つ。
家が寒くなる原因は床にある?
どんなに暖房を効かせても、「床下から冷空気が伝わってきて寒い」「足元が冷え込む」とお悩みの人は多いようです。暖かい空気は上に向かい、冷たい空気は下に降りるという性質があるため、足元は寒くて当然…と思うかもしれません。しかし足元が常に寒い原因は、外気の影響を受けてしまう家の構造にあります。
築年数が古い住宅では気密性が低く、床などに隙間が存在します。この隙間から床下から冷気が入り込み、室内温度を下げているのです。また、床下には、外気を循環させるための外気空間があります。このため床への断熱処理が行われていない場合は、外気の気温がそのまま床に伝わってしまいます。
【床編】北海道で家を暖かくする床断熱とは?
足元の「冷え」を解消するためには、断熱材を床に施工し、断熱性能を高めることが大切です。床断熱の方法は、「床下断熱工法」と「基礎断熱工法」の2種類です。
床下断熱工法とは?メリット・デメリットをご紹介
床下断熱工法は、床材と床下の空間との間に断熱材を入れ、床面が外気の影響を受けるのを防ぐ方法です。床断熱の工法として一般的で、全国的に用いられています。
床断熱工法のメリットは、長年の実績により技術が確立されており、安心して導入できる点です。また、床下の換気口を塞がないため、空気を循環させて結露・白アリの発生を防ぐことができます。基礎や巾木コンクリートもそのままのため、施工費用が比較的安く、リフォームでも施工することが可能です。
一方デメリットは、断熱性能に限界がある点です。いくら床に断熱材を施していても、換気口のある床下空間は外気にさらされている状態です。だからといって断熱材を分厚く施工しようとすると床の高さが必要で、住まいの状態によっては実現できない場合が多いようです。
基礎断熱工法とは?メリット・デメリットをご紹介
基礎断熱工法は、建物の基礎コンクリート自体を断熱材で覆い、床下空間を室内空間にしてしまう方法です。基礎の内側に断熱材を入れる「内断熱」と、基礎の外側を断熱材で覆う「外断熱」があります。
基礎断熱工法のメリットは、断熱材に覆われた床下空間が外気の影響を受けにくい・床に冷気が伝わりにくいところです。床下と室内の温度が変わらないため、高い蓄熱効果も得られます。床下配管などの凍結防止もできる上、収納スペースとして床下を利用することもできるでしょう。
デメリットは、新築時しか施工できないこと、シロアリの発生に気づきにくいこと、床下浸水の被害に遭った場合は自然に排水・乾燥できず、カビなどが発生しやすいことです。ただし、開閉可能な断熱換気口を設けたり、シロアリ対策をしたりすることで、改善することは可能です。
北海道で暖かい家を選ぶ際の基準とは?
ハウスメーカー・ビルダー各社はそれぞれ床断熱に関しても方針を持っています。このため、会社選びがイコール床断熱の施工方式を選ぶことになるでしょう。ハウスメーカー・ビルダー選びをする際は、床下断熱工法か基礎断熱工法、どちらを採用しているか確認してみてください。モデルハウスで実物を見学するのも良いでしょう。
その際は、気密性をチェックするのも忘れずに。どちらの断熱工法でも、気密性が低いと隙間から冷気が入ってきてしまいます。C値の値が小さいほど「外気温に影響されにくい」「気密性が高い」と判断することができます。
寒い冬でも快適に過ごせる家が欲しいなら、床断熱を行いましょう。どんなに壁や窓の断熱に気を遣っても、床からどんどん冷気が上がってきてしまっては心地よく過ごせません。
床断熱を行う場合は、基礎断熱工法がおすすめ。気密性が高く外気の影響を受けにくいため、家全体があっという間に暖かくなります。北海道・東北地域などでは、冬に配水管が凍る心配をしなくて済む点もメリットでしょう。

伊藤修平さん
住研ハウスでは、各パネルヒーターを温める不凍液を送る配管を床下に設置しているめ、(コンクリートの蓄熱効果もあって)床下のほうがむしろ温かいです!